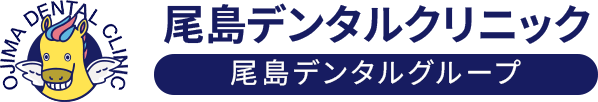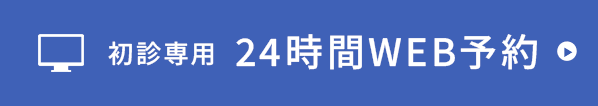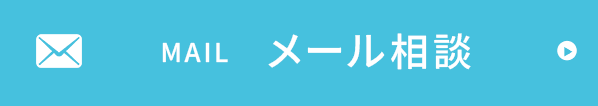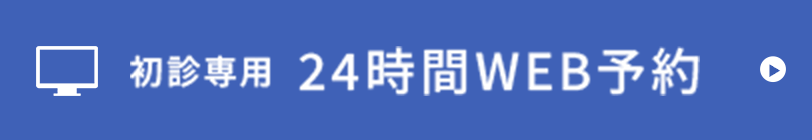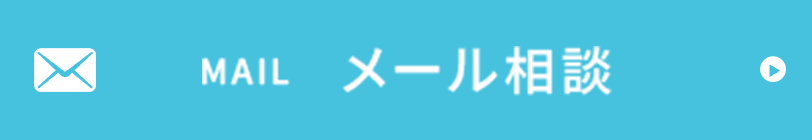2022年09月26日
こんにちは、歯科医師伊藤です。
今回は「インビザラインとゴムかけ」についてお話しします。
インビザラインとはマウスピース型の矯正治療のことで、当院ではありがたいことに多くの患者様にインビザラインを選んで頂き、毎日治療を行っております。
インビザラインはマウスピースを装着するだけで歯並びが改善していく場合が多いですが、マウスピースの他にゴムを使用する場合が稀にあります。
具体的にはマウスピースを装着した後に、白い目立ちにくい小さなゴムを歯の表面につけているボタンに患者様自身に引っかけてもらって使用します。
もちろんこのゴムをかけたとしてもお口を開けて会話もできますし、痛みや違和感もほとんどないので生活に支障をきたすことはありません。
このゴムかけを行う目的は以下の通りです。
一つ目は、例えば上の前歯を後ろに引っ張りたい時などに、マウスピースだけの力だと引っ張る力がうまく歯に伝わらない場合がありますが、ゴムかけを行うことで効率的に前歯を下げることができるようになります。
この目的でゴムかけを行います。
二つ目は、奥歯を咬ませたい時です。インビザライン治療の途中で奥歯が咬みにくくなった際などに、奥歯同士をゴムで引っ張ることで奥歯をしっかり咬ませることができます。
以上のように歯並びの状況によっては、マウスピースだけではなく、補助的なゴムを使用することでより良い歯並びに改善していく場合もあります。
当院では、その患者様にあった最適な治療法を選択し、お口の状況を細かく分析し、精密な治療計画を立てることを実践しております。
今回はインビザラインにおける治療法の一種を説明いたしました。
歯並びのことで気になる部分がある方はぜひご相談ください。
お待ちしております。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
2022年01月12日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日は、わりとよく相談を受ける「〇〇までに〜」についてお話します。
「〇〇までに〜」というのは、患者さんから言われることがあるのですが、具体的には
・自分の結婚式までに〜
・結婚式の前撮りまでに〜
・成人式までに〜
・娘の結婚式までに〜
・高校卒業までに〜
・来月から海外転勤なのでそれまでに〜
といった具合に、治療を〇〇までにしてほしいというご要望です!
結婚式や成人式など、人生の記念すべき日に、ニコッと笑顔で笑えるような綺麗な歯でいたいというのは誰もが思うところだと思います。
そういった患者さんのためにも、僕も間に合うように全力でサポートさせていただきたいのですが、実際には間に合わない場合もあります。
・新しい入れ歯を作ってほしい!来週までに!
・今週末に娘の結婚式があるのでそれまでに前歯の差し歯を作り変えたい!
・来月までに歯並びを綺麗にしたい!
など、入れ歯や被せ物などは作製時間、矯正であれば数ヶ月など、治療に必要な時間が確保できないほど急な場合はご希望に添えないこともあります。
逆に言うと、早めに相談していただければ、その大事な日までに、1番素敵な笑顔になれるように様々な治療を提案させていただくこともできます。
当院のマウスピース矯正は、軽度のものであれば数ヶ月でキレイな歯並びにすることが可能なので、結婚式までまだ数ヶ月〜1年ほど時間があるような場合であれば、当日までに治療を終えることも可能です。
お口の中の状況によっては、みなさんが想像しているよりも治療に時間がかかることがありますので、大事なイベントや記念日までの治療をご希望の方は、まずはお早めにご相談ください。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
👉インプラントについて
2021年07月13日
歯科医師の平形です。
先日、患者さんから「上あごに硬い出来物が出来ていて心配なので見てほしい」というお話がありました。
確認すると、「口蓋隆起」と言われるもので、専門的には「外骨症」といいます。
上の顎に出来るものは「口蓋隆起」、下の顎に出来るものは「下顎隆起」と呼ばれ、どちらも骨の過剰発育から見られます。
多くは、噛み合わせの強さ等が影響していると考えられています。
患者さん自身がお気付きになられた際は、悪性のものではないか?と受診されることが多いのですが、骨の変形ですので心配はありません。
そのため、何か自覚症状がなければ、経過観察になります。
しかし、あまりに大きくなったことで話しにくくなったり、お食事を飲み込みにくくなることもあります。
また、入れ歯を作る際に支障が出る方もいらっしゃいます。
そういったケースは、外科的に切除をご提案することもあります。
先程の患者さんは、口蓋隆起に気付いてから、気にして触りすぎてしまって、赤く腫れ、痛みが出てしまっていました。自然に過ごしていただくことが一番です。
気になる方は、1度クリニックへ相談にいらしてください。
口蓋・下顎隆起の様にわかりやすいものもありますが、頬の粘膜や歯ぐき、舌などの状態の変化には、皆さんなかなか気付かれないことも多いようです。
些細な変化にも対応出来る様に、我々にお口の中を確認させて頂ければと思います。
むし歯や歯周病の治療目的には限らず、3ヶ月に1回程度は、クリニックへ。ぜひお待ちしております。
また、機会があれば、お口の中の粘膜の病気についてお話していきたいと思います
2021年05月21日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
なかなかコロナウイルスの終息が見えず不安な日が続いていますね。
ワクチン接種も始まっていますが、1日でも早く安心して暮らせる世界になってほしいと思います。
さて、本日はそんなコロナウイルスと同じくらい怖い「誤嚥性肺炎」についてお話します。
誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは、誤嚥=食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうこと、から発症する肺炎のことをいいます。
肺炎は日本人の死因の第3位ですが、この肺炎のうち80歳代の約8割、90歳以上で9.5割以上が誤嚥性肺炎であったという調査結果があるそうです。
当院で行っている訪問歯科では、こういったご高齢の方の誤嚥性肺炎を予防する取り組みを行なっています。
誤嚥性肺炎肺炎の原因は様々ですが、主な原因として、
①お口の中が汚れている
②飲み込みが悪い、ムセやすい
が挙げられます。
お口の中が汚れているほど、感染のリスクが高く、ムセやすいほど汚れが肺に入ってしまう確率が高くなります。
この二つを予防するためには、日々の介助者による口腔ケアと歯科衛生士による専門の口腔ケアによってお口の中に汚れが残らないようにすること、また歯科医師による嚥下機能の確認やマッサージなどのリハビリを行うことがとても大切です。
コロナウイルスに注目が集まっていますがらコロナウイルスと同じくらい誤嚥性肺炎は危険です。
誤嚥性肺炎はコロナウイルスのようにワクチンではなく、日々の口腔ケアで予防できますので、ご家族に口腔ケアが必要な方などがいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
2021年05月10日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日はむし歯や歯周病などによって歯を失ってしまった場合にどうしたらいいのか?ということについてお話します。
まず歯を失ってしまった場合、そのままにしておいてしまうと、他の歯が移動してきたり、他の歯の負担が大きくなったりすることで、また次の歯を抜くことになってしまう可能性があるため、基本的には歯を失ってしまったところには、何らかの方法でその部分を補ってあげる必要があります。
どんな方法があるかというと、主な治療法は以下の通りです。
①義歯
いわゆる入れ歯です。
金属のバネを残っているご自身の歯にかけることで、失った歯を補う取り外し式の治療法です。
お口の中に入れた時の違和感が大きく、噛む力も弱いため、硬いものやお肉などが噛みにくいことが多いです。
②ブリッジ
前後の歯を削り、被せ物でつなぐ治療法です。
義歯とは違い、ご自身で取り外すことはできません。
噛む力はご自身の歯と比べると7〜8割ほどの力を発揮しますが、その分支えにしている前後の歯が早めに悪くなってしまう可能性があります。
また、つながった被せ物なので、歯磨きの際につながっている部分の清掃が難しいことも特徴です。
③インプラント
歯を失った部分に、人工的な歯を埋め込む治療法です。
失った歯を治す治療の中で最も噛む力が強く、硬いものも違和感なく噛むことができます。
また、前後の歯を削ったり、他の歯に負担をかけることもないため、残っているご自身の歯にとっても優しい治療です。
ただし、骨の状態や全身疾患など、状況によってはお選びいただけない可能性があります。
ざっとではありますが、一般的に歯を補う治療法にはこのようなものがあります。
そのまま歯を抜いたままにしておくと、あとで治したくなったときに治すのが難しくなってしまいます。
当院では、歯を失ってしまった場合の治療相談についても、しっかりと一つ一つの治療法のメリットデメリットをご説明させていただいておりますので、歯を失ってしまってお困りの方がいましたら、ぜひご相談ください。
2021年03月23日
むし歯は誰が作っているのか。
こんにちは、歯科医師の菅原です。
そろそろ春になってきて少しずつあったかくなってきましたね。皆さんいかがお過ごしですか?
前回の続きで今回もむし歯は誰が作っているのかを説明していきます。
前回口の中の菌が歯の周りや歯茎に溜まって行くと、プラークやバイオフィルムを作り、そうすると悪さをし始める事を説明しました。
そこに糖分を与えると、菌が糖分を食べて酸を出し始めます。
ですがまだこの段階では弱い酸なのでそれほど歯は溶かされません。まずはプラークやバイオフィルム内にいる菌に影響を及ぼして行きます。
どんな事が起こるかと言うと、酸に弱い菌が減って酸に強い菌ばっかりになります。
酸に強い菌は酸が好きなのでどんどん酸を出します。
すると口腔内の菌の種類に変化が起きて環境が変化します。
こうなるとどんどん酸を溶かして歯を溶かしてむし歯を作ります。
こうなってしまうと口腔内の状態を改善するのは難しくなってきます。
現代では糖を摂取しないのはかなり難しいので、他の人と同じ食生活を送っていただけでもむし歯になります。
皆さんはむし歯は誰が作っているのか予想がつきましたか?
もちろん狭く言えば口の中の菌です。
ですが口の中の菌は皆さんに存在しているので、国民全員がむし歯じゃないと説明がつかなくなります。
なので、むし歯を作るのは自分自身口の中の認識や気持ちだと思います。
むし歯になりやすいからしょうがないと思っている患者さんがいれば当院で一度診察を受けてみてはいかがでしょうか?
尾島デンタルクリニックではむし歯のなりやすさの検査である唾液検査なども希望者に実施しています。
総合的にお口の中がどの程度むし歯に対してリスクがあるかを診断できます。
自分がどのくらいむし歯になりやすいかを知るだけでお口の中の悩みへの対応が見えてくるかもしれません。
興味がある方は是非当院のスタッフに遠慮なくお伝えください。
次回はむし歯をどうやって予防するかを説明していきます。
2021年03月18日
こんにちは、歯科医師の今野です。
先日、口腔機能発達不全症についての院内勉強会を行いました。
密にならないように3回に分けて行いましたが、希望者のみの参加にも関わらず、ほぼ全員のスタッフさんが参加してくれました。
このように皆が勉強熱心なところが、この歯科医院の本当に素晴らしいところだな、と感じています。
さて、その勉強会の内容ですが、
むし歯以外で子どものお口の健康の問題となっている様々な機能的な問題についてお話ししました。
たとえば
よく噛まない・早食いする
食べるのに時間がかかる
柔らかいものばかりを好んで食べる
お口がポカンと開いている…など
最近はこのようなお口の機能に問題のある子供が増えています
現代のお子さんは、スマートフォンやゲーム機で遊ぶことが増えたため、昔の子供がよくやっていたような、わらべ歌を歌いながらの手遊びやお顔をつかった「にらめっこ」など、お口や全身を使った遊びが減ってきています。
お口の機能を育む上で、上述のような遊びが重要になってきます。
また、スマートフォンやゲーム機で遊んでいるときの悪い姿勢もお口の機能に悪い影響を与えます。
お口の周りの筋肉のバランスが悪いと、歯並びやかみ合わせの問題を引き起こしたり、むせやすくなり、誤嚥・窒息しやすくなってしまいます。
適切な時期に適切な機能を獲得できるようにトレーニングが必要です。
私自身、子供の頃から食べるのが遅く、よく親に怒られてストレスになっていました。
食事の時の姿勢も悪く、食事のたびに指摘されていたのに治すことができず、歯並びやかみ合わせが悪くなってしまったので、大人になってからの矯正治療が必要になってしまいました。当時は気にならなかった歯並びも大人になるにつれて気になっていくものです。
あの時、ちゃんとお母さんの言うことを聞いて姿勢を正していれば、子供の頃からお口の機能を治していれば、と勉強するほどに後悔しています。
今の子供たちには自分のような後悔をしてほしくないので、子供のうちから歯並びを悪くするような悪い癖や姿勢を正し、お口の周りの不十分な筋力を鍛えるように指導しています。
子供は自分では自分のお口の状態が良いのか悪いのかわかりません。
早いうちから保護者の方が気づいてあげることが大切です。
何かお気づきのことがあれば一度受診していただき、ご相談ください。
2021年02月6日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
今日は「インプラント」について説明していこうと思います。
最近ではインプラントという言葉をみなさんもよく耳にしているかもしれませんが、実際にどういうものなのかを詳しく知らない方も多いかもしれません。時々入れ歯や差し歯のことをインプラントだと勘違いされて来院される方もいらっしゃいます。
そこで本日はインプラントについて簡単にご説明します。
インプラントとは、簡単に言うと、ご自身の歯を抜歯しなくてはいけなくなってしまった場合に、抜歯した後に同じ位置に人工的な歯を手術で埋め込む治療法のことをいいます。
インプラント=手術=怖い
と思われる方も多いかもしれません。
しかし実際は簡単な場合には手術も30分程度で終わります。
そして麻酔も全身麻酔ではなく、むし歯治療や抜歯をする時に使用するものと同じ局所麻酔(部分麻酔)で行います。
痛いんじゃないの?という質問もよく受けますが、基本的には抜歯の際と同じ程度の痛みが出るくらいで、みなさんが想像しているよりも痛みが出ることは少ないかもしれません。
歯を失ってしまった場合にブリッジや義歯などの治療法もありますが、隣の歯を大きく削るなど、残っている他の歯を傷つけて寿命を縮めてしまうのに対し、インプラントであれば他の歯には手をつける必要はありません。
ただし、インプラントは骨がしっかりしているかどうか、全身疾患(糖尿病や高血圧など)の有無など事前の検査が必要です。
当院ではインプラントの相談やインプラントが可能かどうかの相談などの無料相談もお受けしておりますので、気になる方は一度ご相談ください。
👉インプラントについて
2021年01月4日
こんにちは、歯科医師伊藤です。
当院で行っているマウスピース矯正「インビザライン」についてのお話しをしていきます。
今回はインビザラインと歯の抜歯についてです。
ガタガタの歯並びを矯正で治す際には抜歯が必要な場合と必要ではない場合があります。
ガタガタ度合いが少なめの場合は、歯と歯の間に隙間を作ったり、歯並びを拡大することで抜歯をしなくても綺麗な歯並びを獲得することができます。
一方、ガタガタ度合いが強く、隙間を作っても改善できない場合には抜歯が必要になります。
矯正する際に抜歯が必要なのかどうかを判断するには、お口の中をスキャンしてその場でシミュレーション画像を見ることで判断が可能です。
歯並びのガタガタがコンプレックスだったり、他院で抜歯が必要と言われたけど抜歯はしたくない、などお悩みの方がいらっしゃいましたら、矯正無料相談は随時受け付けておりますので是非ご相談下さい。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
2020年11月27日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
先日、外出している間にカバンの中に入れておいたマウスピースのケースを愛犬に取り出され、ボロボロにされていました。マウスピース本体は装着していたので無事でした…
ご自宅で、犬や猫を飼われている方は、矯正装置や取り外しの歯(ケースも含めて)にいたずらをされないように注意しましょう!
さて、今回は、根管治療中に起こる腫れについてお話をさせていただきます。
腫れが生じる原因は、管の中の清掃が進み、管の中にいる細菌が一時的に活発化して、管の外で悪さをするためです。
特に、根管治療が行われずに神経が死んでしまい、長年経過した歯の治療を開始したときに起こりやすいといわれています。
腫れが生じた際には、管の中から膿をだし、管の中を洗浄します。また、暴れている細菌を抑えるために抗生剤を数日間服用していただきます。
その後は、通常の根管治療同様に器具を用いて、管の中を徹底的に清掃していき、きれいになった段階で最終的なお薬を詰めていきます。
治療を開始しても、根の管の中は複雑なため、痛みや腫れを生じることがあります。
根管治療中で、悩みがある方はいつでもお気軽に質問してください。