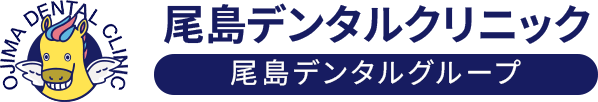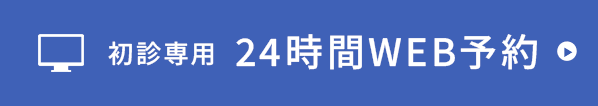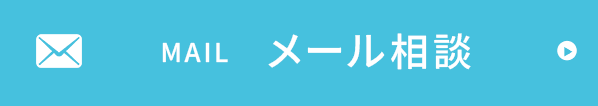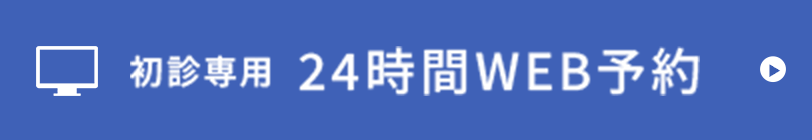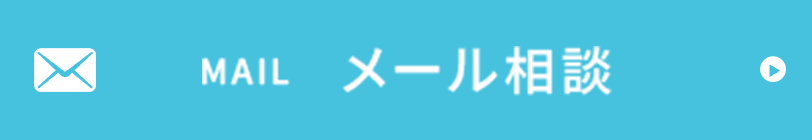2024年10月24日
こんにちは、歯科医師の深谷です。
歯科治療には大きく分けると保険治療と自費治療の2種類があります。
どちらにもメリット・デメリットがあります。
それらを正しく理解し、納得した上でより自分に合った治療を受けることが大切です。
今回はそれらについて詳しくお話をしていこうと思います。
保険治療の最大のメリットは、国民皆保険制度に基づき、日本国民であればだれでもどこでも安価な治療費で一定の質が担保された治療を受けることができることです。
この制度は国民全員が毎月支払っている保険料をもとに、病気にかかってしまった方を支える素晴らしい仕組みです。
この制度がなかった時代は、治療を受けたくても受けられず、苦しい思いをした方が沢山いらっしゃるそうです。
その反面、皆のお金を使い、約1億2千万人いる日本国民全員を対象としているので、厳密なルールや制限があります。
具体的には、良い材料が使えない、適応できない治療方法があるなど、1人1人の細かな要望に応えられない可能性があることがデメリットです。
また、この制度は実施されてから60年以上経過しているため、改良はされていますが、現代のニーズにそぐわない面もあります。
つまり保険治療は、大勢に適応する平均的な方法で、最良ではないが、痛みを取り除いたり、失った機能を取り戻すことで、最低限生活に困らないようにすることが目的の治療方法です。
その一方、自費治療の最大のメリットは、制限がないので、日々進化する最先端の技術や方法、材料などを使うことができ、最良の治療、1人1人のニーズに合わせたより質の高い治療を提供できることです。
つまり、自費治療は、痛みを取り除いたり、失った機能を回復するだけにとどまらず、口腔内の問題を解決することで、QOL(生活の質)の向上を目指すことを目的とする治療方法です。
そのため、保険治療と比較すると治療費が高額になるのがデメリットですが、より質が高く自分にあった治療を受けることで、理想の自分に近づくことができます。
個々の治療によって他にもメリット・デメリットがあり、その時の状況によってベストな治療方法も異なります。一度お口の中を拝見させて頂ければ、皆さんにあった治療方法を提案できますので、お気軽にご相談ください。
2024年08月21日
こんにちは
歯科医師の熊澤です。
年齢が上がるに連れてむし歯や歯周病、歯の破折などが原因で歯を失ってしまうことがあります。
1本なくなっても全然ごはん食べられるよ!問題ないんじゃないか?
と考える方もいらっしゃいますが、本当にそうでしょうか?
今回は歯が少なくなっていく過程をお話しします。
食事を行う際、上下の歯を咬み合わせることで食べ物を細かくしています。
ここで歯が1本減るとしましょう。
①1本減ることでその周りの歯の負担が大きくなる
(例えば3本の歯で負担していたものを2本で負担するため、負担は1.5倍となります)
②負担が大きくなる、周囲の歯が磨きにくくなるなど不都合が生じる
③歯周病や破折のリスクがあがる
④歯を失う
⑤そのままにする
②~⑤を繰り返すことで少しずつ歯を失っていくことになります。
歯を失った際にそのままにしておかずに対応することが重要です。
治療する方法はインプラントやブリッジ、入れ歯などがあります。当院では治療方針についてしっかりお話しした上で治療を行なっていきます。
歯を失ったまま、なんとなく放置している方はいないでしょうか?お気軽にご相談ください。
2024年05月22日
皆さんこんにちは、歯科医師の深谷です。
今回は治療の中断の危険性についてお話をします。
「痛みがなくなった」、
「仮の歯で問題なくかめる」、
「回数が多くて面倒くさい」、
「仕事が忙しい」
などの理由で治療を中断してしまったことはないでしょうか?
実はそれ、とても危険です。
虫歯治療の場合、なるべく早期に治療を行うことで、歯を削る量を最小限に抑え、治療回数も費用も少なくすることができます。
虫歯治療を中断すると、虫歯がどんどん進行し、やがて神経にまで広がり、何もしていなくても痛みを感じるようになります。
神経まで虫歯が広がると、根の治療が必要になり、治療回数や費用が増えます。
また、ご自身の歯を削る量も多くなります。
根の治療を中断すると、細菌が根の先端の方まで広がります。
根の先端まで細菌が到達すると、歯茎が腫れて痛みがでたり、膿がでたりします。
最悪の場合、抜歯に至ります。
歯周病治療も同様で、細菌が歯を支える骨にまで広がると抜歯になる可能性があります。
歯を1本でも失うと、インプラントやブリッジ、入れ歯など、より期間や費用のかかる治療が必要になります。
いずれにしても治療途中で通院をやめてしまうと、取り返しのつかない状態になり、後々さらに大変な治療が必要になってしまうので、根気よく通院しましょう。
当院の歯科医師、歯科衛生士、スタッフが全力でサポート致しますので、一緒に頑張りましょう!
2023年12月12日
こんにちは。歯科医師の深谷です。
だんだんと寒くなってきましたが体調に気を付けていきましょう。
今日は食生活と歯ぎしり・食いしばりについてお話をします。
歯がかける、起床時にあごがこわばっている、夕方になると頭痛がする等の経験はありませんか?
これらの症状が頻繁に生じる方は、歯ぎしり・食いしばりをしている可能性があります。
そもそも歯ぎしり・食いしばりはブラキシズムと呼ばれ、以下の3つに分類されます。
1.グラインディング:歯をギリギリ擦り合わせること
2.クレンチング:歯をグッと食いしばること
3.タッピング:歯をカチカチ噛み合わせること
上記の歯ぎしり・食いしばりがあると以下の健康リスクが高まります。
1.歯がかける
2.虫歯、歯周病
3.顎関節症
4.頭痛、肩こり
歯ぎしり・食いしばりは、お口の健康だけではなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすため、早期に改善することが重要です。
歯ぎしり・食いしばりを生じる主な原因はストレスと言われていますが、普段の食生活も影響しています。
特に就寝前に糖質の多い食事を摂るとリスクが上がります。
就寝前に糖質の多い食事を摂ると、食後に上がった血糖値が睡眠中に一気に下がります。
それを回復させるためにアドレナリン等のホルモンが分泌され、血糖値が一気に上がり、血糖値の乱高下が起こります。
これがストレスになり、交感神経が優位になって、歯ぎしり・食いしばりの原因になります。
歯ぎしり・食いしばりの改善のためには、まず、普段のストレス度合いをチェックし、生活習慣の改善が必要です。
それに加えて、食事内容や食事のタイミングを見直していきましょう。
これらを意識することで、歯ぎしり・食いしばりだけでなく、全身の健康状態の改善にも繋がっていきます。
当院では管理栄養士による栄養指導もおこなっております。
ご自身だけでは改善が難しいと感じる方は、是非ご来院ください。
2023年08月21日
こんにちは、歯科医師の大藤です。
暑い日が続いていますね。夏バテや疲れを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
疲れが溜まったときに、ふと「痛っ」と感じお口の中を鏡で見ると大きな口内炎が、、、なんて経験をしたことがあるのではないでしょうか?
口内炎があると、お食事が思いっきり楽しめず、つらいですよね。
口内炎は多くの方が経験したことがある疾患です。しかし、一口に口内炎といっても、実ははっきりとした原因は分かっておらず、様々な種類、原因があると言われています。
ビタミン不足や睡眠不足、ストレス、免疫力の低下によるウイルス感染、ホルモンバランスの乱れ、ブラッシングによる損傷や粘膜を傷つけやすい歯並び、なかには服用中の薬剤や全身の疾患によりできるものもあります。
直径0.3~1㎝程度の円形または楕円形で、灰白色または黄白色の膜に覆われ、縁が赤くなって痛みを伴います。
口内炎ができてしまったら、残念ながら治るのを待つことにはなりますが、治りを促してくれる方法をご紹介していきます。こちらは、口内炎の治りを促進してくれますが、もちろん予防にも繋がりますので、まだできていないという方やよくできてしまうという方にも参考になれば幸いです。
まず、口内炎ができるのは頬粘膜や舌、歯茎ですので、粘膜の清潔と強化を意識し、ストレスに負けない身体を作るための栄養を摂取すると良いです。
粘膜の清潔に重要なのは、何よりも日々のブラッシングです。食後や就寝前のブラッシングはもちろん、なるべく毎回隅々まで丁寧なブラッシングを心がけましょう。口内炎ができている部分には刺激が加わらないよう力を入れすぎず、優しく磨きましょう。
粘膜の強化には、栄養素が深くかかわると言われ、中でもビタミン群の摂取が効果的です。特に、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンCの多い食材が特におすすめです。
・ビタミンA:皮膚や粘膜の健康維持
(含まれる食材)レバー、カボチャ、ニンジンなど
・ビタミンB2:粘膜の保護
(含まれる食材)レバー、ウナギ、納豆、アーモンドなど
・ビタミンB6:皮膚や粘膜を生成
(含まれる食材)カツオ、マグロ、鮭、鶏肉、玄米、バナナなど
・ビタミンC:抗ストレス作用
(含まれる食材)ブロッコリー、柑橘、緑茶など
このほか、口内炎に対する生活習慣のアドバイスとしては、お酒やたばこを控えることや、女性の場合は鉄分の多い食材の摂取を心がけるとより良いです。
歯科医院では塗り薬としてステロイド系の軟膏などを処方することもありますが、自分自身を労わることが予防、治癒への一番の近道です。
いかがでしたか?口内炎ができてしまったら、まずは自分の生活を振り返り、十分な休息を取って、厳しい暑さの夏を乗り越えていきましょう!
2023年01月6日
皆さん、こんにちは。歯科医師の平形です。
朝晩も冷え込み、私も日に日に、暖房に頼りっきりとなり、その分”乾燥”とも戦う日々にございます。
皆さんは何かの『乾き』にお悩みではないでしょうか?
私は”ドライアイ”で、夕方になると症状に苦しむこともあります。同じお悩みの方もいらっしゃることと思います。
また、患者さんから『口の乾き』について相談されることも度々ございます。
目の乾きは涙、お口の乾きは唾液が影響していますが、どちらも体内の水分量と関係します。
1日の水分の摂取量の目安として、「2リットルのお水を飲んでね」という目標をよく耳にすると思います。
実は、一般的な唾液量も1日に1.5リットルほどになります。
ほかにも尿や汗、涙・・・水分はあらゆるところで必要になるため、もともとの水分の摂取量が足りなければ、至るところで、枯渇して、カサカサしてきてしまうわけです。
唾液量が少ないと、滑舌が悪くなります。ヒリヒリしたり、ネバネバするような感覚がある方もいらっしゃいます。
そして唾液には、お口のバランスを整える機能があります。そのため、唾液量が少ない人は、むし歯や歯周病が進行することも考えられます。
もちろん、唾液量の低下は水分量による影響だけでなく、加齢や病気も原因として挙げられます。
唾液線を刺激するマッサージもおすすめしておりますので、こちらは次回の私のブログでお伝えできれば、と思います。
これからの季節、皆さん寒いとなかなか水分を摂取することに意識が回りにくくなるものです。
水分が足りなければ、なにも乾燥するだけではなく、高血圧や脳梗塞のリスクにもつながります。
いつもより少し意識をして、コップ1杯をプラスして飲む習慣をつけてみると、体内の水分バランスが整えることが出来るかもしれません。
そんな日常の小さなきっかけから、皆さんの健康をサポートさせていただければと思います。
今、この文章をPCで打ち込む自分の指を見たら、ささくれが見つかりました。
アルコールでの手指消毒が生活に定着しているこの時代では、ハンドクリームも手放せませんね。
乾燥を好むウイルスたちに打ち勝つためにも、しっかり保湿していきましょう。
2022年07月23日
こんにちは、歯科医師の今野です。
このコロナ禍におけるマスク生活で、「口臭が気になる」という患者さんが増えたように思います。
口臭の悩みというのはセンシティブな悩みなのでなかなか周囲に相談できず、深刻に悩んでいらっしゃる患者さんもいらっしゃいます。
では、口臭の強い人が増えているのか、というとそういうわけではなさそうです。
「口臭」と一言で言っても、臨床的には3つの種類に分けられます。
① 自臭症(非病的口臭):
歯科的にも医科的にも病的な口臭を認めないが、患者が主観的な自覚的な臭気に悩んでいる場合。
② 他臭症:
直接的な原因となる病的問題から発生する病的口臭で悩む場合。
③ 仮面他臭症
はじめは他臭症であったが、問題となる病的口臭が完治したにもかかわらず、自臭症に陥る場合
実は口臭に悩む約80%の方は、①自臭症であり、病的な問題を持たないといわれています。
反対に、病的な問題を持つ②他臭症の方は、臭気が常に存在するために患者自身では自覚しにくく、他人の指摘を受けて受診することが多いといわれています。
こちらは口臭を主訴に来院される方の約20%未満です。
では、病的な原因のない自臭症の方は、どうして口臭に悩んでしまうのでしょうか?
それは、人の嗅覚の特徴として、一度気にしてしまうと、嗅覚の閾値が低下し、微量な臭気であっても強く気になってしまうようになる、ということが原因としてあげられます。
特に今はその臭気がマスクの中に停留するので余計に気になるのでしょう。
そもそも「自臭(自覚的・非病的口臭)」とは、治療の必要のない生理的口臭(起床時や空腹時、緊張時などに一時的に起こる口臭)や社会的容認限度内の微細な口臭であって、かつては、気にしないように説明されるか、精神的な問題として扱われてきました。
しかし、それだけでは解決されず、口を閉じがちになったり、人前で会話を控えるようになり、コミュニケーション阻害が生じてしまうこともあります。
当院では、実際に口臭がどの程度あるのか、原因物質は何かをガスクロマトグラフィーを用いて調べる口臭検査を行っています。
「自臭」であることが分かればそれだけで気持ちが楽になる方もいらっしゃいます。
ご希望の方はお気軽にご相談ください。
2022年07月5日
こんにちは、歯科医師の熊澤です。
みなさんは虫歯治療後にしみる経験をしたことはありますか?
痛みはなかったのに、治療したらしみる症状が出た経験をした人もいるでしょう。
治療後にしみる原因はおおまかに2つあり、むし歯の大きさと治療時の刺激です。
まず1つ目のむし歯の大きさですが、歯の内側には痛みを感じる神経があります。
むし歯が大きくなるほど神経との距離は近くなり、しみる症状は強くなります。
2つ目の治療時の刺激ですが、むし歯の治療では高速回転させた器具を使用します。
水を出しながらではありますが、摩擦による熱刺激が神経に伝わります。
むし歯の治療中は麻酔が効いているため痛みは感じませんが、麻酔が切れてくるとしみる症状が出てくることがあります。
ただししみる症状がずっと続くわけではありません。
数日で落ち着く方もいれば数カ月かかる方もいます。
しみるくらいなら治療しない方が良かった!と思う方もいるかもしれません。
むし歯の中には痛みもなくジワジワと進むものもあります。
気づかず放置することによってズキズキとした耐えられない痛みに変わり治療が大掛かりになる可能性もあります。
むし歯は早期発見・早期治療が大切です。むし歯を見つけたり、痛みを感じたりしたら早めの受診を心がけましょう。
次回はしみる症状が落ち着いていく原理についてお話していきます。
2022年04月4日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日はむし歯になりやすい食べ物についてお話します。
むし歯になりやすい食べ物に共通する特徴として、
・歯にくっつきやすい食べ物
・口の中に長く残る食べ物
・糖分が多い食べ物
などがあります。
一番イメージしやすい食べ物で言うと、「キャラメル」はその代表です。
他にはアメやチョコレートなども挙げられます。
糖分の含まれる飲み物などもむし歯になりやすい食べ物と言われており、コーラやスポーツドリンクなどがその代表です。
また、見落としがちな食べ物として、僕が注意してほしい食べ物の一つが「のど飴」です。
風邪をひいた時や喉が痛い時に、1日中のど飴を舐めていたり、寝る前に舐める、そのまま寝てしまうなんて経験はありませんか?
のど飴を薬のような感覚で使用している人が意外と多いかもしれませんが、のど飴にも糖分が入っています。
最近では、代用甘味料などむし歯になりにくい糖分で作られた食べ物も増えてきています。
当院では、小さなお子さまがむし歯予防をしながら食べられる「むし歯になりにくいチョコレート」や「むし歯になりにくいグミ」などの販売も行っておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください!
2022年01月29日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日はこどもの歯並びについてお話します。
最近5〜10歳くらいのお子さんの歯並びのご相談を受けることが多くなってきており、世間のお父さんお母さんがお子さんの歯並びに興味を持っていただけてることがすごく嬉しいです。
子どもの頃に治しておいた方が良い!と思っている方が多くいらっしゃるのですが、まさにその通りで歯並びは早くに治療した方が長い目でみた時に良い結果が得られることが多いと思います。
実際には「早く治療した方が良い」というよりは「早めに相談した方が良い」という方が正しいかもしれません。
というのも、この年齢のお子さんの歯並びは大人の歯(永久歯)とこどもの歯(乳歯)が混在することが多いため、
・いつから始めるのがベストなのか?
・今だったらどの治療法を選ぶといいのか?
・今は様子を見てていいけど、〇歳くらいになったらやった方が良い
などが、その子のお口の中の状況で変わります。体の成長に個人差があるように歯の生え変わりの時期にも個人差があるので、同じ年齢であってもひとりひとりお口の中は同じではありません。
中には、あとで生えてくる予定の大人の歯が生まれつきない!なんてこともあります。そう言った場合にも、ないことを早めに知っておくことで、ベストな時期にベストな治療を選択することができます。
お子さんの歯並びは、治療自体は今すぐでなくても、早めに一度相談しておくと、このままで良いのか?いずれは治療した方が良いのか?を判断することが出来ますので、もしお子さんの歯並びでお悩みの方がいれば、お気軽にご相談ください。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について