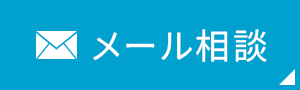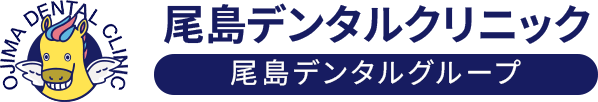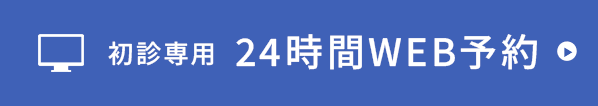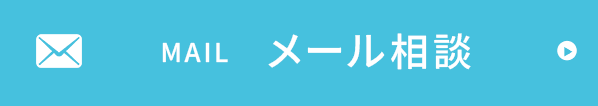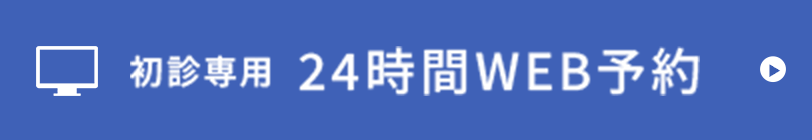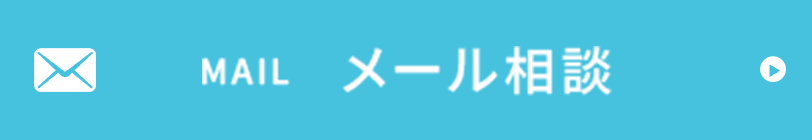2019年09月13日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
私たち尾島DCの歯科医師、スタッフは日常的な仕事以外にも、休日は都内のセミナーや勉強会に積極的に参加して知識を深めています。
私自身もここ数ヶ月は毎週のように、都内で開催されるセミナーに参加させていただいています。中でも熱心に勉強しているのは、セラミック治療についてです。
セラミックが銀歯よりむし歯になりにくい、見た目が綺麗、体に優しいなどといったことは、みなさんもご存知かもしれませんが、一概にセラミックと言っても、実はセラミックにもいろんな種類があります。
そこで今回は、セラミックの種類について、ご紹介したいと思います。
セラミックとは、お皿や包丁などにも使われている陶材のことで、汚れがつきにくく、綺麗なことから、歯科の詰め物や被せ物としても活用されています。
尾島DCで取り扱っているセラミックもいくつか種類がありますが、大きく分けると以下の4つになります。
【ハイブリッド】
セラミックとプラスチックを混ぜた材料です。
セラミックが入っているため、通常のプラスチックの詰め物などと比べると、削れにくく、色も綺麗です。
しかし、セラミック100%ではなく、プラスチックも半分混ざってしまっているため、時間とともに色が変色してしまったり、噛む力に耐えきれず割れてしまうというトラブルも多い材料です。
【セレック】
セラミック100%で人間の歯とほぼ同じくらいの硬さをもつ材料です。
セラミックの中でも加工しやすく、作製にかかる時間も短いため、型取りからお口に入れるまでを1時間ほどの予約時間内で終えることができるので、治療が1日で終わるということが最大のメリットです。これなら仮蓋や仮歯も入れる必要がありません。
【e-max(イーマックス)】
セレックよりも硬いセラミックで、見た目も綺麗な材料です。
削り出したあとに、高温で20〜30分焼きあげなくてはいけない為、手間もかかりますが、その分透明感があり、より歯の色に近い仕上がりです。
奥歯など、噛む力がかかりやすい部位にオススメです。
【ジルコニア】
セラミックの中で最も硬い材料です。
e-maxよりも綺麗さは劣りますが、とにかく頑丈で、割れることはほとんどありません。
歯ぎしりが激しい方や入れ歯のバネがかかる歯など、力がかかりやすい歯に使用します。
というように、セラミックには種類があり、それぞれこのような特徴があります。
もしかすると「いろいろあって選べない!」という方もいるかもしれませんが、治療する歯の部位や用途によって選択が変わってきますので、尾島DCの歯科医師・スタッフが最適な材料をみなさんと一緒に考えていきますのでご安心ください!
何かご不明な点などあれば、お気軽にご相談ください(^ ^)
2019年09月10日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
先日、久しぶりにサッカーをしたのですが、翌日に全身筋肉痛になってしまいました。
日頃から運動をしておくことの大切さを改めて実感しました。
さて、みなさんはTCHという言葉についてご存知ですか。
TCHとは、Tooth Contacting Habit(歯牙接触癖)のことをいい、日中食事をしていない時でも、ずっと弱い力で、上下の歯を噛み合わせてしまっている状態のことをいいます。
基本的に、食事や会話をしていない時間では、上下の歯は噛み合わさっておらず、隙間が空いている状態です。
接触をしている時間は、24時間のなかで、食事や会話を含めても平均17.5分程度ととても少ないのです。
TCHは何か作業に集中している時(例えば料理や運転など)、ぼーっとパソコンやスマートフォンを操作している時にも出現することがあります。
上下の歯が常に接触していることにより、咬む筋肉が常に緊張している状態になります。
その状態がさらに続くと、首や肩の筋肉にまで緊張が波及し、全身の疲労や筋肉のコリに繋がっていってしまうのです。
簡単なTCH対策としては、TCHがあることを認識し、自分自身で歯と歯を接触させないように意識することです。
お部屋の数カ所に、「歯を噛み合わせないように」と付箋などで貼っておくと、より気付きやすくなると思います。
自分のストレスを感じない範囲で、少しずつ意識して改善するようにしましょう。
何か不明点などありましたら、遠慮なく歯科医師、スタッフにお聞きください。
2019年08月29日
こんにちは、⻭科医師の菅原です。
夏本番!皆さんどの様にお過ごしでしょうか?
⼤好評の「本当は怖い⻭周病シリーズ」の第3弾です。
今回は⻭周病がどんな病気なのか掘り下げたいと思います。
⻭周病とはお⼝の中の細菌の感染による炎症性疾患です。
炎症性疾患というのは要するに、腫れる、⾚くなる、熱を持つ事です。
⻭の周りには⻭周ポケットと⾔われる隙間が有るのですが、そこに汚れが溜まると菌の量が増え、菌が悪さを始めます。悪さを始めると、⻭茎が充⾎して⾚くなり少し腫れた感じになります。
この状態になると、⾎のめぐりが多いのでブラッシングで簡単に出⾎を起こす様になります。
これが患者さんの良く⾔う「⻭を磨いていたら⾎が出てきた」という状態です。
こうなると患者さんは痛いので⻭ブラシをしなくなります。⻭ブラシをしないと汚れが無くならないので、どんどん⻭周病が進⾏します。
⻭周病が進⾏するとそうなるかと⾔うと⻭を⽀えている顎の⾻が吸収されてし
まいます。
顎の⾻が吸収されると、⻭が揺れてきて最悪の場合抜⻭となってしまいます。
ここまでの話の中でどこが⻭周病を⽌めるポイントだと思いますか?
正解は⻭⾁を腫れさせないという事です。
その為には、汚れを⼝の中に貯めないという事が重要です。
つまり⽇々のブラッシングが⼤切と⾔う事です。
当院では定期的なメンテナンスを通して、⼝腔内の汚れを徹底的に落とし、患者
さんにあったブラッシングを指導していきます。
これを⾏う事によって汚れを落として菌の量を減らし、⻭⾁の出⾎が起こるのを抑えます。
皆さんメンテナンスの重要性を理解して頂けましたか?
⻭周病がいかに怖い病気なのかを知ってもらえたら幸いです。
2019年08月14日
こんにちは、歯科医師の今野です。
この頃テレビで芸能人を見ていると歯並びの良い方ばかりだなあと感じています。
さて、歯並びの良い人・悪い人はどうやって決まるのでしょう。
遺伝でしょうか。
実はそうとも限りません。
歯並びの悪くなる原因には大きく分けて
①遺伝的要因(あごの大きさなど)
②後天的要因(生活習慣・癖)
の2つがあります。
お口の「癖」が原因の場合、歯並びも予防することができます。
今日はこの後天的要因についてお話します。
歯並びが悪くなる原因となるお口の悪い癖を口腔習癖といいます。
たとえば口呼吸・指しゃぶり・舌の使い方等々…
こういった悪い癖は、子供のうちから放置しておくとどんどん歯並びが悪化してしまいますが、子供のうちにしっかり治しておけば、将来的に起こり得る歯列不正を予防できる場合があります。
お子さんの様子を見た時に
・お口をポカーンと開けている
・口呼吸をしている
・唇が荒れている
・上下の歯の間から舌が見える
・会話時に舌がよく見える
・硬い食べ物を嫌う
・食べこぼしが多い
・姿勢が悪い
・指しゃぶりなどの癖がある
などといった兆候があったら注意が必要です。
口腔習癖を放っておくと、歯列や咬合などの見た目の問題だけでなく、
「噛む」
「飲み込む」
「話す」
「呼吸する」
といったお口の機能全般に影響を及ぼすことになります。
心当たりのある方はぜひご来院の際にご相談ください。
次回は口腔習癖によってどのように歯列不正が起こるのかについてお話しします。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
2019年07月23日
こんにちは。
歯科医師の菅原です。梅雨の季節になり夏本番が目の前ですね。
さて今回は当院で行なっている位相差顕微鏡と歯周内科について掘り下げて説明します。
前回の僕のコラムでも書いてある様に、位相差顕微鏡はお口の中の菌を視覚的に確認します。
まず患者さんの口の中からプラークを取ります。プラークとは菌の塊で口の中の汚れです。
そのプラークを特殊な顕微鏡で観察します。
その時に何を観察するかと言うとズバリ〝菌の量、菌がどれだけ動いているか、菌の大体の形〟です。
皆さん菌の種類を見ているかと思うかもしれませんが、あの顕微鏡では大まかな形しかほとんど判りません。例えば球体なのか線状なのかという感じです。
菌の量が多く菌が元気だと、いくら歯石取りやクリーニングなどの歯周病治療を行なっても中々歯周病は良くなりません。
もちろん位相差顕微鏡で大体の形である程度判別できる〝やばい菌〟もいます。
らせん状菌(スピロヘータ)、真菌、歯肉アメーバ、トリコモナスと言う菌です。
これらの〝やばい菌〟がいたり菌の量が多く元気な時には、当院では抗菌薬を投与し、口腔内の状態をリセットすることもあります。
もちろん口腔内の状態をリセットしただけなので、日々の歯ブラシや定期的なメンテナンスを怠るとまた元の状態に戻ってしまいます。
また真菌が多くいることもあります。
真菌はいわゆる口の中のカビ菌でこれに作用します。
真菌は酸を出して歯を溶かしてむし歯になりやすくなったり、口腔粘膜に張り付くと痛みが出たりします。
口腔内のカビ菌を減らし、むし歯になりにくい口腔内を作って行くことも大切です。
この様に顕微鏡で口腔内の菌を確認し、薬の力で歯周病の治療の手助けを行う事を〝歯周内科〟と言います。
尾島デンタルクリニックではこの様に歯周内科を行なって行く事で患者さんの歯周病を管理していきます。
もちろん歯周内科だけで歯周病は治りませんし、歯周病菌は口腔内の常在菌がほとんどなので、完治する事はありません。
なので定期的なメンテナンスとご自身のブラッシングが重要です。
2019年07月16日
こんにちは。歯科医師の今野です。
最近、学校歯科健診の結果を持った子供たちがたくさん来院される時期になりました。
知らず知らずのうちに進行していくむし歯。みなさんは大丈夫ですか?
そもそも、どうやってむし歯はできるのでしょうか。
むし歯は歯の表面についた細菌が砂糖から酸を作り、その酸が歯を溶かすことによって起こります。
ですから、むし歯予防は、
①歯みがきによる細菌の除去
②食生活の見直しによる砂糖の適切な摂り方
③歯の表面を溶けにくくするフッ化物の応用
の3つの方法によって行います。
今回は②食生活の見直しによる砂糖の適切な取り方についてお話しします。
みなさんはおやつを何回食べていますか?
「何回」というのは甘いものが口の中に入った回数を数えます。
キャラメルだったら間食の回数は中身の包み紙を開けた回数だけ増やすカウントです。
ペットボトルのジュースはの場合はだらだらと飲み続けられますから、おやつの回数として数えられるカウントはとても多くなります。
一般的に間食の回数が増えれば増えるほど、むし歯になりやすくなります。
ですから、おやつは時間を決めてだらだら食べないことが重要です。
また、健康に良いと思って頻繁に飲んでいる飲み物ありませんか?
たとえば乳酸菌飲料やスポーツドリンク、野菜ジュースなど。
この中にどれだけの砂糖が含まれているかご存知ですか?
実はたった65mlの乳酸菌飲料にもスティックシュガー4本分の砂糖が含まれています。
スポーツドリンクには約8本
果汁100%ジュースや野菜ジュースにも約7本分の砂糖が入っています。
これが何度もお口の中に入るので、実はとってもむし歯になりやすいんです。
最近、天然水のような見た目をした透明のフレーバードリンクがありますが、あれも見かけによらず、お砂糖がたくさん入っているので注意が必要です。
砂糖を取りすぎてしまうと、むし歯になりやすいだけでなく、健康も害してしまうので、特にお子さんに飲ませる時には注意しましょう
歯磨きはしっかりしているはずなのになぜかむし歯になってしまう…。
そうお悩みの方、
原因は食生活や、他の部分にあるかもしれません。
尾島デンタルクリニックではひとりひとりの原因に応じたむし歯予防を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2019年07月10日
こんにちは。歯科医師の平形です。
みなさん、お薬手帳はお持ちですか?
内科の先生に受診された際、何かお薬を処方されていると、薬剤師さんから手帳の有無も確認されていると思います。
歯医者さんに受診する際、お薬手帳は必要ないように思っていらっしゃる方も多いかと思いますが、実はみなさんのお口を診ていく上で、すごく大事な役割を果たしてくれます。
尾島デンタルクリニックでは、初めて受診して下さった方と、まず、お話する時間を頂いております。
単に、どの歯が痛むか?ということだけではなく、みなさんの全身的な体調などもお尋ねすることもあります。
もちろん、プライベートな部分ではありますが、治療していく上で、現在受診しているご病気があるか?、過去の病歴や飲まれているお薬、アレルギーなどをお尋ねしております。
歯の治療に関係あるの?と思われる方もいらっしゃると思いますが…歯科処置も出血したりすることもありますし、お薬を処方することもあります。
すると、血液がサラサラになるお薬を飲まれている方の出血が伴う処置には、通常以上の注意が必要になります。また、お薬を飲まれている方、我々が処方するお薬との飲み合わせやアレルギーなどを考えなくてはなりません。
ぜひ、お聞かせ頂けますと、より安全に歯科治療に臨むことができますので、よろしくお願いします。
こういった病気やお薬の進化は、日進月歩。日々、勉強が必要になります。我々尾島デンタルクリニックのドクター、スタッフは常に新しい情報を学ぶために、勉強しております。

写真は、先日のセミナーのものです。飲み込む能力をトレーニングするためのリハビリを学んできました。鼻からチューブを入れているところです。
治療時に感じた疑問は、我々になんでも質問して下さい。
2019年06月27日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
夏の気配が漂いはじめる気候になってきましたね。
私もだんだんと半袖で過ごす機会が増えてきました。
さて、本日は、むし歯の進行具合についてお話をさせていただきます。
歯はエナメル質、象牙質、歯髄から出来ていて、むし歯は、歯のどこまでむし歯が及んでいるかで分類がされています。
Co(初期エナメル質う蝕)
歯の冠部分(エナメル質)の表面がざらざらしている状態です。他の冠部分より少しにごったような感じや奥歯の溝が茶色くなったような見た目です。
このむし歯は、他のむし歯と違って、歯磨きやクリニックに通っていただきクリーニングを行っていくことで、自然に治っていくことがあるのが特徴です。
C1(エナメル質う蝕)
先ほどのCoよりも、むし歯が進行している状態です。
痛みがないため、自分で気付いた時には、さらに進んだ虫歯であることが多いです。
むし歯を削ってプラスチックの材料を詰める治療が必要になります。
C2(象牙質う蝕)
人の体で一番硬いといわれるエナメル質に穴が開き、次の層である象牙質にまでむし歯が進行した状態です。象牙質は、エナメル質よりも軟らかいため、むし歯の進行のスピードが速いのが特徴です。
外側のエナメル質は小さい穴でも、中の象牙質ではむし歯が広がっていることもあります。象牙質にまで達すると、痛みや違和感が出てくることがあります。
むし歯を削った後は、プラスチックの材料を詰める治療または型取りを行う治療が必要になります。
C3(歯髄まで達したう蝕)
むし歯が、象牙質に穴を開け、神経(歯髄)まで達した状態です。
この状態になると、何もしていなくてもズキンズキンと痛むようになってきます。神経にまで、むし歯が達してしまった場合には、むし歯の細菌によって、神経が感染を起こしてしまっているため、神経を取り除く治療が必要になります。
放って置いた場合、神経は死んでしまい、根の先までむし歯の細菌が進んでいき、歯の周りの骨にまで影響を与え、痛みや腫れを生じることがあります。
C4(歯冠が崩壊し、根だけの状態のう蝕)
むし歯が大きく進行し、歯の冠部分が全部なくなり、根だけになった状態です。
根の治療が厳しい場合には、歯を抜く検討をすることもあります。
いかがでしたでしょうか。むし歯の進行具合によって行う治療が変わってきます。
当院では、目ではわかりにくいむし歯の早期発見のために、ダイアグノデントという機械をもちいて診査を行っております(ホームページの、むし歯治療の項目に詳細が載っているのでご覧下さいね)。
出来るだけ早くむし歯を見つけて、進行を防ぎましょう。
2019年06月12日
本当に怖い、歯周病!?
こんにちは!歯科医師の菅原です。
めっきり暑くなってきましたね。今からこんなに暑いと夏本番が怖いですね。
今日は意外と知られていない、歯周病と全身の病気のお話です。
歯周病は日本人の8割以上が感染している感染症です。
一般的に知られているのは、臭いや歯が抜ける原因になるって事じゃ無いでしょうか?
歯周病は単なるお口の中の事だけではなく、全身の健康状態とも密接に関わっています。
歯周病が関係する全身の病気はこんなにあります。
- 糖尿病
- 心筋梗塞
- 低体重児、早期出産
- 誤嚥性肺炎
- アレルギー
- 便秘
特に心筋梗塞と誤嚥性肺炎は高齢者の死因の上位に上がってくる病気です。
歯周病ってこんなにも多くの病気に関係している事に驚く方も多いともいますが、これらの死因の患者さんを調べてみると、歯周病の病原菌が多くの確率で肺や心臓から検出されます。
これらの病気を予防する方法は、毎年人間ドックに通うのと同じように、定期的に歯科医院に通い口腔内の歯周病菌を把握し、衛生士さんのクリーニングとブラッシングで歯周病菌を効果的に減らす事です。
当院では、定期的に患者さんのお口の中の菌を取って位相差顕微鏡で菌の画像をお見せします。『うわ、こんなに菌っているの?』って驚かれるかも知れません。
どんな菌が居て、どの位菌が活動的なのかを知る事で、それぞれの患者さんのお口の中にあったブラッシングや歯磨き粉を提案し歯周病菌を確実に減らして行きます。
歯周病の予防には自宅での歯磨きがとても重要になってくるので、一緒に頑張って行きましょう。
何か不明な点などありましたら、遠慮なく来院時に歯科医師、スタッフにお聞きください。
2019年05月19日
こんにちは、院長の林崎です。
すっかり季節も春になりまして、暖かくなってきましたね。
もうすぐ梅雨に入ってしまいますので、個人的には今が一番過ごしやすい時期なのではないかなと思っています。
さて、本日は知っておくと何かと便利な「乳歯と永久歯の違い」についてお話しします。
特に一人目のお子様のお口や歯のことは新米ママさんなどはとても悩むことが多いので、少しでも参考になれば幸いです。
「本数」
乳歯は全部で20本、永久歯は28本です(永久歯は親知らずを抜いた数になります)食べるものの違いもですが、歯が生える顎(あご)の大きさが違いますので、本数にはかなりの差があります。
「色」
実は色も違います。簡単に表現すると乳歯のほうが白っぽくて、永久歯のほうがクリーム色をしています。時々、「うちの子の歯が生えてきたのだけれど、色が変!」と慌てて相談に来る方がいらっしゃいますが、ほとんどのケースは単なる色の違いなので心配はいりません。
ですが、たまに形成不全といって本来の色ではないこともありますので、心配な方は遠慮なくご相談くださいね。
「硬さ・むし歯のなりやすさ」
細かい違いはいっぱいあるのですが、一番大事なことはこれです。
乳歯はやわらかく、永久歯よりもとてもむし歯になりやすいのです。むし歯かな?と思っていると、乳歯の場合は一気に深くなることがあるのは、これが理由です。
歯磨きを頑張ることはもちろん、定期的に歯医者さんで診てもらうことや、フッ素やシーラントで予防することが大事です。
もちろん、永久歯も乳歯よりもむし歯になりにくいと言っても、むし歯にはなります。特に生えてから2年くらいは歯が完全に硬くなっていないので、とてもむし歯になりやすい時期です。この時期は乳歯と同様に予防に力を入れるのが良いと思いますよ。
一生使う永久歯はもちろん、乳歯も大切な働きがありますので「抜けるから」などと思わずに大事にしていきましょう。
何か不明点などありましたら、遠慮なく来院時に歯科医師、スタッフにお聞きくださいね。