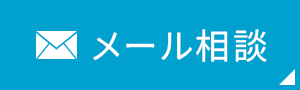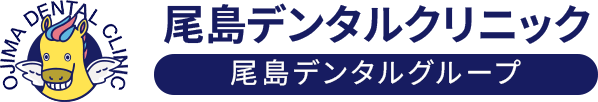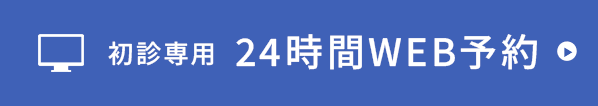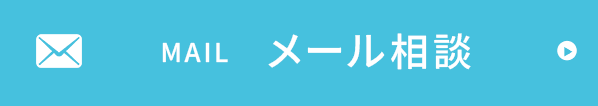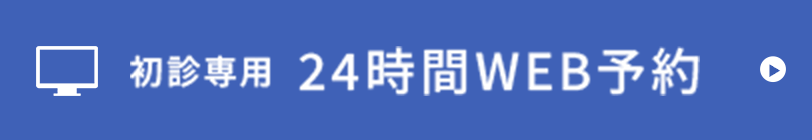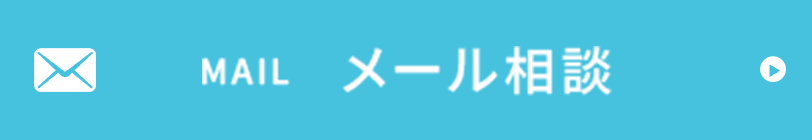2023年06月20日
こんにちは。歯科医師の鈴木です。
みなさん「SDGs」ってご存知ですか?
テレビやインターネットなど、日本だけでなく世界中で進められている取り組みです。
SDGsとは「持続可能な開発目標」を意味し、2015年に国連で採択され、2030年までの国際社会共通の目標になっています。
SDGsでは、17の大きな目標を定め、2030年までの達成を目指しています。
尾島デンタルクリニックは、このSDGsの取り組みを積極的に行っている歯科医院です。
今回は当院で実施しているSDGsの取り組みの一部をご紹介しようと思います!!
■目標1 貧困をなくそう
こちらは世界中で貧しい暮らしをしている人々を助けるという目標です。当院ではこちらの目標達成に向けて様々な募金活動を行っています。最近ではウクライナ募金、トルコ募金など、当院の歯ブラシや歯磨き粉などの物販の売上の一部を募金するという取り組みを行いました。
■目標4 質の高い教育をみんなに
あらゆる人たちが質の高い教育を受けられるようにするという目標です。当院では、セミナーや勉強会への参加を積極的に行うことで日々知識や技術の向上を目指しています。また、小さなお子さまがクリニックの待ち時間に宿題などができるように待合室に学習スペースも設けています。
■目標6 安全な水とトイレを世界中に
■目標14 海の豊かさを守ろう
海などの環境や水という資源を守っていくための目標です。トイレの節水など日常的に資源を無駄にしないことはもちろんですが、地域の環境を守るという観点から当院では月に一度、ド派手な黄色いジャンパーに身を包み、クリニック周辺のゴミ拾い活動も行っています。もし見かけたら手を振っていただけると僕たちもうれしいです!
この他にも17の目標達成に向けて僕たちに出来ることを日々全力で取り組んでいます!
尾島デンタルクリニックのホームページやInstagramでも、SDGsの取り組みについては紹介していますのでぜひご覧ください(^_^)/
2023年05月19日
こんにちは、歯科医師の深谷です。
突然ですが皆さんは何を基準に歯科医院を選んでいますか?
コンビニより数が多い歯科医院。
数が多いと便利ではありますが、良い歯科医院とそうでない歯科医院の見分けがつけにくく、
どこを選べばよいかわからなくなりますよね。
業界のタブーとも言えるこんな疑問について僕の考えを率直にお伝えできたらと思います。
治療が上手い、先生が優しい、患者数が多い、最新の設備がある、消毒滅菌がしっかりしている、医科の先生との連携、ホームページやカウンセリングが充実している、家から近い等、
良い歯科医院の指標は沢山あります。
ですが、選択する皆さんからすれば、指標が沢山ありすぎると
どこが良い歯科医院かわかりにくいと思います。
食や見た目を通じて人生に大きな影響を与える歯科医院選び。
このBlogを通してなるべく多くの皆さんが良い歯科医院に出会えることを願っています。
その中で、実際に歯科医師として歯科医院で働く私が最も重要だと感じ、
これをおさえておけば間違いないと思う指標をお伝えします。
それは、スタッフの定着率!!!
実際に内部で働くスタッフは、良いことも悪いことも全て知っています。
設備やホームページは充実していても先生がいい加減な治療をしているような歯科医院には、
スタッフは定着しません。
当院は新卒3年目のスタッフの定着率が100%です。
この数字が全てを表しています。
結婚や出産などで一時的に職場を離れるスタッフもいますが、
皆復帰して活躍してくれています。
その理由は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保育士、管理栄養士、歯科助手等、
全職種が、常に患者さんに最良な治療を提供するために働いているからに他なりません。
全職種が仕事に誇りを持ちそれぞれの役割を果たしています。
その結果として、新卒3年目スタッフの定着率が100%を達成し、
多くの患者さんが当院を選んで通院して下さっています。
また、スタッフのご家族の方々も当院を選んで通院して下さっています。
当院はスタッフがご家族に自信をもって紹介できる歯科医院です。
通院するたびにスタッフが入れ替わっている、
ホームページにうつっていないスタッフばかりいる、
スタッフの表情が暗い等の歯科医院は少し注意が必要かもしれません。
当院は治療が上手い、最新の設備がある等のことは当然として、
患者さん一人一人に合わせた最善の治療を提供しています。
今後歯科医院選びに困った際には、是非参考にしてみて下さい。
2021年09月8日
こんにちは、歯科医師伊藤です。
今回は「歯の再矯正」についてお話しします。
歯の再矯正とは、過去に矯正治療を行っていたが、また歯並びが悪くなってしまいもう一度追加で行う矯正治療のことを言います。
海外では日本より矯正治療を受ける子供が多いので、再矯正を行う人も多いと言われています。
また、これは動いてしまったから仕方なく行うというマイナスなものではなく、体の成長に応じた必要な追加治療であると考えられています。
なぜ再矯正を行う必要が出てしまうのかというと、歯並びは常に変化するからです。
矯正終了後の一定期間は保定装置という歯並びがもとに戻らないようにする装置を装着することが多いですが、一定期間を過ぎると保定装置を使わなくなります。
それでも歯の位置は常に変化しているので、生理的な範囲で歯が動いてくることがあります。
その時に歯並びが気になる場合ははもう一度矯正治療を行う必要が出ます。
しかし、過去にワイヤー矯正を行っていた方の中にはもう一度ワイヤーを張ることに抵抗を感じる方も多くいます。
その場合、再矯正にはアライナー矯正治療が適していると考えています。
アライナー矯正治療とはマウスピース矯正治療のことです。
当院で行っているアライナー矯正治療であるインビザラインも透明なマウスピースを装着して矯正治療を行う方法です。
この方法はワイヤーに比べると、違和感や歯磨きの難しさが少なく受け入れやすい矯正治療といえます。そのため、再矯正に適しているといえるのではないでしょうか。
状況にもよりますが、再矯正は前歯だけの部分矯正で対応できる方も多く、比較的短時間で費用負担も少なく行える場合もあります。
お口の状況により変わりますので、過去に矯正をしていた方も含めて歯並びでお悩みの方はご相談下さい。状況に応じた最善の方法をお伝えしていきます。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
2021年05月10日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日はむし歯や歯周病などによって歯を失ってしまった場合にどうしたらいいのか?ということについてお話します。
まず歯を失ってしまった場合、そのままにしておいてしまうと、他の歯が移動してきたり、他の歯の負担が大きくなったりすることで、また次の歯を抜くことになってしまう可能性があるため、基本的には歯を失ってしまったところには、何らかの方法でその部分を補ってあげる必要があります。
どんな方法があるかというと、主な治療法は以下の通りです。
①義歯
いわゆる入れ歯です。
金属のバネを残っているご自身の歯にかけることで、失った歯を補う取り外し式の治療法です。
お口の中に入れた時の違和感が大きく、噛む力も弱いため、硬いものやお肉などが噛みにくいことが多いです。
②ブリッジ
前後の歯を削り、被せ物でつなぐ治療法です。
義歯とは違い、ご自身で取り外すことはできません。
噛む力はご自身の歯と比べると7〜8割ほどの力を発揮しますが、その分支えにしている前後の歯が早めに悪くなってしまう可能性があります。
また、つながった被せ物なので、歯磨きの際につながっている部分の清掃が難しいことも特徴です。
③インプラント
歯を失った部分に、人工的な歯を埋め込む治療法です。
失った歯を治す治療の中で最も噛む力が強く、硬いものも違和感なく噛むことができます。
また、前後の歯を削ったり、他の歯に負担をかけることもないため、残っているご自身の歯にとっても優しい治療です。
ただし、骨の状態や全身疾患など、状況によってはお選びいただけない可能性があります。
ざっとではありますが、一般的に歯を補う治療法にはこのようなものがあります。
そのまま歯を抜いたままにしておくと、あとで治したくなったときに治すのが難しくなってしまいます。
当院では、歯を失ってしまった場合の治療相談についても、しっかりと一つ一つの治療法のメリットデメリットをご説明させていただいておりますので、歯を失ってしまってお困りの方がいましたら、ぜひご相談ください。
2021年04月8日
こんにちは、歯科医師の今野です。
春になりました。
4月は新しい仲間が増えたり、学年が上がったり、新しい環境になったりと、新鮮な気持ちになるので、わたしの大好きな季節です。
普段こちらのブログでは、患者さん向けに歯科知識について書くことが多いのですが、今日は進路に悩んでいる若者に向けて歯科という仕事の素晴らしさについてお話しさせてください。
わたしは両親が歯科医師でしたので、幼少期から歯科という仕事がとても身近に感じられました。
家の近所を歩いていると、見知らぬ女性から
「あら、歯医者さんの娘さん。いつもお母さんにはお世話になっているわ」
「お母さんに治してもらって、なんでも食べられるようになったのよ」
と笑顔で声を掛けられることもあり、子供ながらにとても誇らしかったのを覚えています。
私たちの仕事は、ただ「むし歯による痛みを取り除くこと」だけではありません。
食事すること、お話しすること、呼吸すること
そんなお口の機能を整えることでみなさんが健康で文化的な素敵な生活を送るためのお手伝いをすることだと思っています。
「お前のお母さんはすごいな、むし歯がなくなったら仕事がなくなってしまうのに、むし歯をなくす仕事をしているんだから」
と言われたことがあります。
言われた当時はきょとんとしてしまいました。
今は、そうではない、と言えます。
歯科医師の仕事はそれだけではない、むしろむし歯なんてなくなってしまえ、と思っています。
あまり知られていませんが、むし歯治療や歯周病治療だけでなく、機能の治療も私たちの仕事です。
たとえば年齢を重ねて、歯がなくなってしまい、形態的問題で食事がしにくくなってしまったり、唾液が出にくくなったり、飲み込むのに必要な筋力低下によりむせやすくなってしまった方はだんだん食べられるものが減ってきて、身体が弱ってしまいます。
そのような方には食べたり飲んだりといった機能のリハビリテーションが必要です。
また、幼少期からしっかり噛んだり飲み込んだりする機能が育っていないと高齢になったときに食事できなくなってしまうリスクが高まりますので、幼少期からしっかりした機能を育ててあげることが大切です。
子供たちの「なりたい職業ランキング」上位に歯科医師や歯科衛生士などの歯科関係の職種が入っているのを日本では見たことがありません。
一方、アメリカでは常に上位に入っています。
少子高齢社会の今だからこそ、日本においても歯科の大切さがみなさんに浸透して、たくさんの若者に歯科界を目指してほしいと願っています。
ぜひ歯科医院でわたしたちと一緒に患者様のQOLを高めるお仕事に励んでいきましょう。
2020年12月24日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
有難いことに、通っていただいている患者さんから時々頂き物をします。
お菓子や果物、旅行先のお土産などいろんなものを頂いたことがありますが、先日初めて頂いたものがありました。
それは、、、
「マスク」
です。
オシャレな手作り布マスクを頂きましたー!!!
歯科医師という仕事なので、コロナウイルス流行前からも毎日マスクは生活に欠かせないものでしたが、コロナウイルスが流行してからはなかなかマスクも手に入らない時期もあり、マスクの大切さを痛感しました。
コロナウイルスがなければ、このような素敵なマスクを頂くこともなかったかもしれないので、まだまだ世界的に大変な時期が続いていますが、人の温かさが伝わってくるこのマスクとともに、コロナウイルスから解放される日を信じて、引き続き仕事に励んでいきたいと思います!
お名前は出せませんが、大切に使わせていただきます!
ありがとうございました(^-^)
2020年10月22日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日は当院の診療室についてご紹介したいと思います。
現在、尾島DCではユニット(診療台)が全部で21台あるのですが、全てのユニットが個室または半個室になっています。
特に歯周病治療やメインテナンスを行う際は、みなさんにできる限り落ち着いた空間で処置を受けていただけるように基本的には個室のユニットへご案内させていただいております。
いつも通ってくださっている方はご存知の方が多いかもしれませんが、尾島DCの個室はすべての部屋にテーマを設けており、壁紙や置かれている物を変えています。
具体的には、
「海」「白樺」「チリ」「桜」「ムーミン」「地中海」「パンダ」「ラベンダー」「ログ」「ニューヨーク」
というテーマに沿った個性豊かな個室が10部屋あります。
この中に入ったことのある部屋はありますか?
まだ入ったことのない部屋も多いと思いますので、10部屋全てを体験できるようにこれからも治療やメインテナンスにお越しくださる際の楽しみの一つにしていただければと思います!
もしお気に入りの部屋や入ってみたい部屋がありましたらスタッフまでお声がけください!
2020年08月11日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
暑い日がつづいていますね。
体調を崩さないように、水分補給は定期的に行うようにしましょう。
さて、今回は根の治療についてお話をさせていただきます。
一度、神経の治療をして、再度根の先に膿の袋ができてしまった場合…
再度、根の治療を行う必要があります。
根の治療を始めていくと、ときに患者さんから「すでにこの歯は神経がなくなっているのに、どうして管の中を触られると痛むのですか」と尋ねられることがあります。
質問にお答えすると、この原因は何種類かあります。
①根の先の穴から感染した歯茎の組織が管の中に入り込んでいる感染した歯茎の組織に痛覚が残っているため、器具で触った際に痛みが出ます。
②根の先まで器具が到達したときの圧圧を感じることで歯の周囲に痛みを感じることがあります。
③根の先から器具の先が出る
根の先まで器具が到達し、先端の組織と触れることで痛みが出ることがあります。
④前回の治療で、神経が先に残っている可能性としては低いですが、時に神経の一部が残っていて、触れたときに痛みが出ることがあります。
上記のように、いくつか原因がありましたが、痛みの回避のために、治療前に麻酔を行うことをおすすめしております。
痛みが苦手な方がいらっしゃいましたら、治療前にお気軽にお声がけください。
2020年05月15日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
新型ウイルスによる自粛生活の中みなさんいかがお過ごしでしょうか。
早く外で思いっきり楽しめる日々を取り戻したいですね!!
さて、本日はそんな新型ウイルスに負けないくらい本当は怖い
『誤嚥性肺炎』
についてお話しします。
誤嚥とは、食べ物や唾液などが、本来は食道を通って胃へと入っていくところを、誤って食道ではなく気道に入ってしまうことを指します。
そして、その誤嚥により、バイ菌や雑菌などが肺へ入ってしまい引き起こしてしまう病気を誤嚥性肺炎と呼んでいます。
肺炎は日本人の死亡原因のトップ3に入ることは有名ですが、80歳以上の高齢者が引き起こす肺炎の約9割以上はこの誤嚥性肺炎だと言われています。
その理由としては、高齢者は嚥下機能(飲み込み)が低下し、誤嚥の確率が上がってしまうこと、そして免疫力の低下によって誤嚥した場合にそのまま誤嚥性肺炎を罹患してしまう可能性が非常に高いことが挙げられます。
では、どうしたら予防できるのか。
嚥下機能の低下による誤嚥については、訪問歯科などで嚥下機能の評価や訓練を行い、またその人の嚥下機能の状態に合わせた適切な食形態(通常食、刻み、ペーストなど)で食事を行うことが大切です。
免疫力の低下については、お口の中を日頃から清潔に保つことが何より大切です。お口の中が清潔に保たれていれば、万が一誤嚥をしてしまった場合でも、肺へ感染する可能性も低くなります。
ご自身で歯磨きや口腔ケアができない高齢の方の場合は、介助されている方がしっかりと毎日口腔ケアを行うことがとても大切です。
正しい食形態?
嚥下機能の評価?
口腔ケアの介助?
など、お口の中をキレイにした方がいいのは分かっているけど、具体的にどうしたら良いか分からない方も多くいらっしゃると思います。
尾島デンタルクリニックでは、こういった食形態の相談や口腔ケアのやり方の指導、歯科衛生士によるプロの口腔ケアを行なっています。
新型ウイルスで命の危険を感じて過ごす中、お口の中を清潔にすることはその予防の第一歩です。歯科医院になかなか歯科医院に通えない方やそのご家族の方、一緒にこの危機を乗り越えていきましょう!
訪問歯科についてのご相談など、ぜひ気軽にお問い合わせください。
2020年05月9日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
だんだんとあったかくなってきましたが、まだ朝晩は冷えますね。
体調を崩さないように注意しましょう。
さて、今回は子供のむし歯予防に使われるシーラントについてお話したいと思います。
シーラントは、奥歯の溝を塞ぐことでむし歯を防ぎます。
乳歯の奥歯や生えたての永久歯の奥歯は背が低く、磨きにくいためむし歯になりやすいのです。
そこで、奥歯の溝をあらかじめ埋めておくことで、むし歯が発生進行するのを予防することができます。
シーラントには、フッ素含有の樹脂(プラスチック)が用いられます。
この材料から、お口のなか全体にフッ素がだんだんと広がっていくのとともに、歯磨き粉の中に含まれるフッ素をシーラントが取り込み、むし歯を予防することができます。
シーラントは歯を削る必要がなく、歯の表面を磨いた後に、材料で溝を埋めて、光で固めておしまいです。
ただ、シーラントをしたからといって、むし歯にならないわけではありません。
歯磨きをきちんとしないと、溝ではなく、歯と歯の間や歯と歯茎の境目がむし歯になってしまうので、毎日仕上げ磨きをしましょう。
また、シーラントは永久的に持つものではなく、かけたり、取れたりすることもあります。
そのかけた部分からむし歯になることもあるので、シーラントの状態がどうなっているか定期的に確認する必要があります。
お子さんが何でも美味しく食べられるように、お口の中を一緒に守っていきましょう!